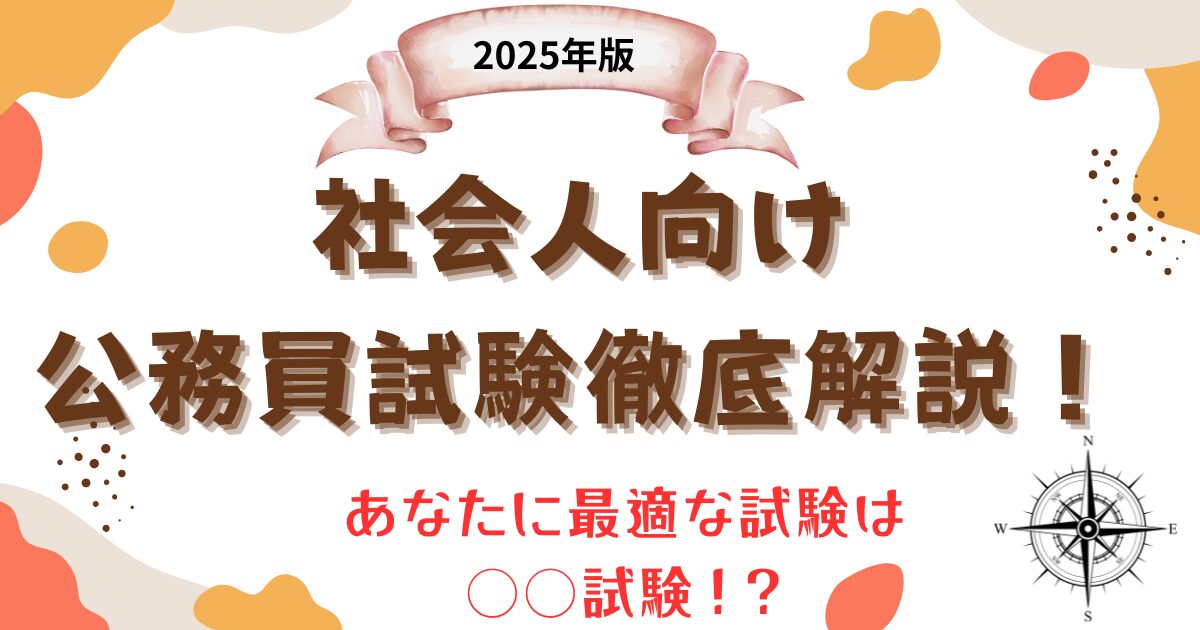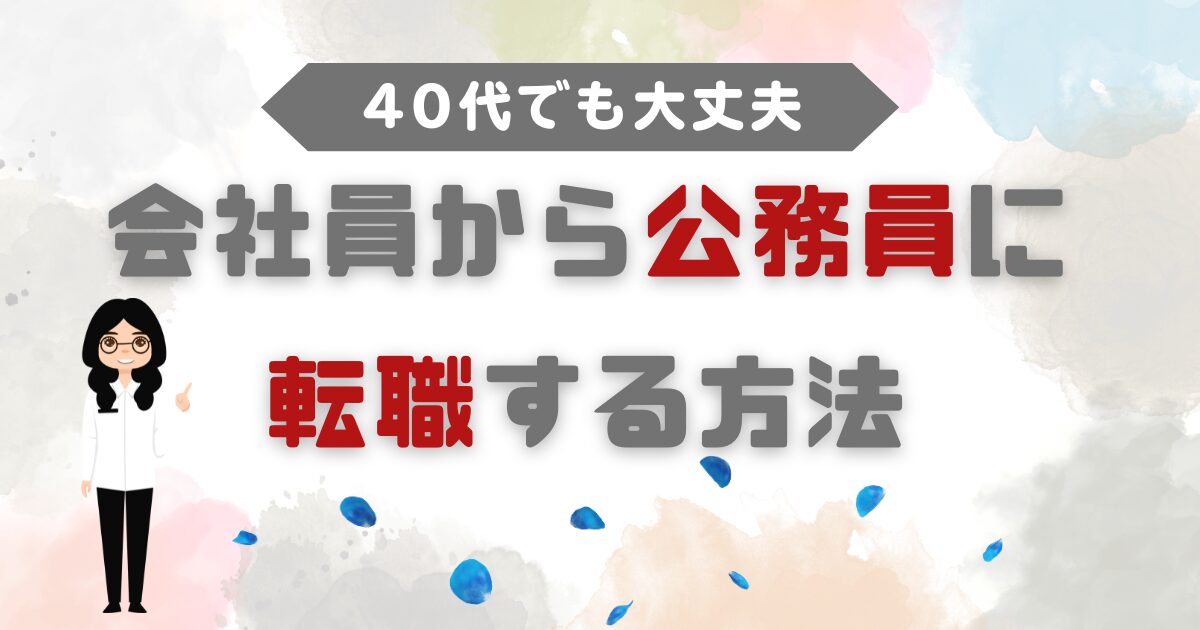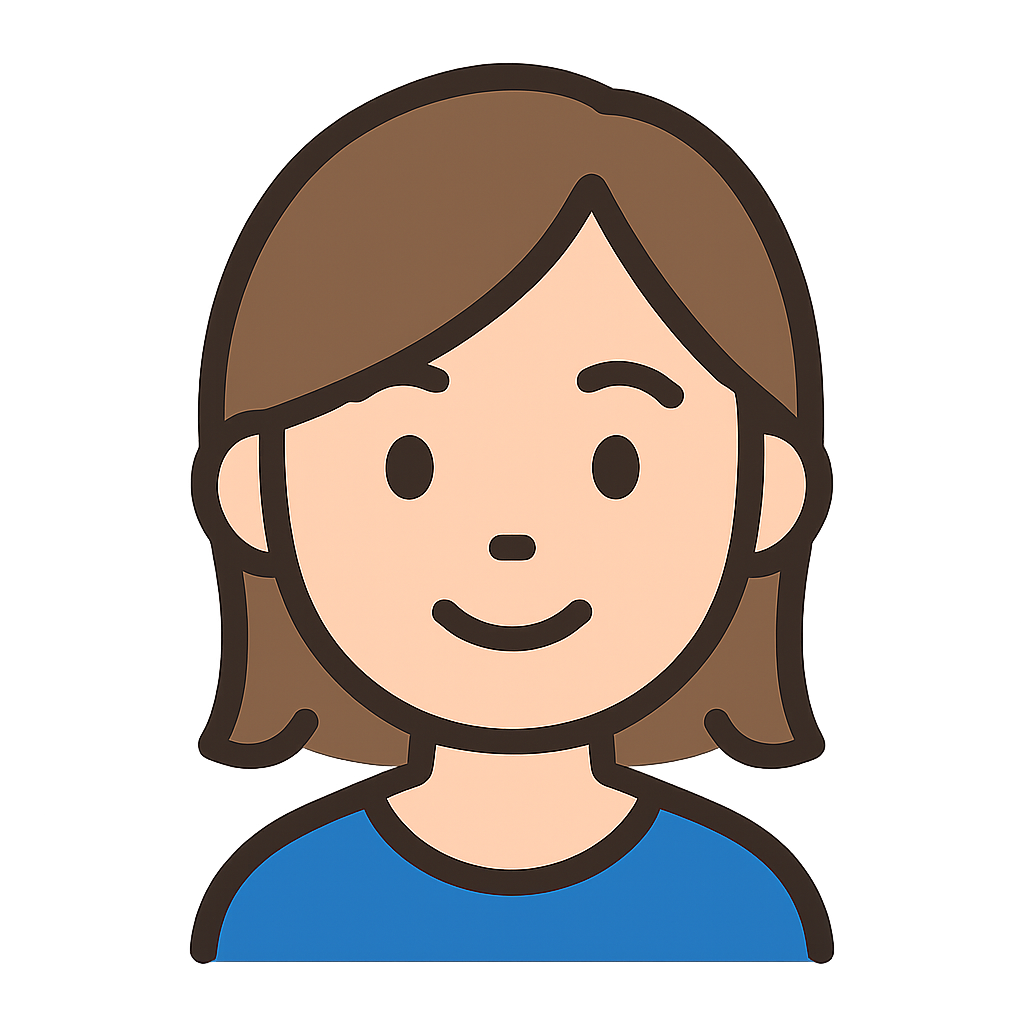
公務員への転職に挑戦したいけど
私は、転職後に職場に馴染めるのか気になるな
地方自治体の中途採用枠は年々増えてきています。2024年度は全都道府県で募集が行われています。
年齢制限の上限は59歳までと、実質年齢制限を設けない自治体もあるくらいです。
また、職務経験者として採用されると、今までのキャリアを考慮した給与体系になる場合があります。
選考試験は、一般教養試験と論文や面接という試験科目が主流であり、学科試験の重みが低いことが特徴です。
このため、現在の仕事を公職に活かし、住民のために役立てたい!と考えている方にはオススメの転職といえます。
一方、公務員の文化は、民間企業とは違う独特の作法やルールがあります。
筆者は中途採用で県庁職員になり、「今までの仕事の仕方が通じない」そうストレスを感じる同僚を見てきました。
キャリアアドバイザー
IT系の民間企業に20年勤務(転職有り)
公務員8年勤務
働きながら公務員への転職を志す
半年間勉強し県庁と市役所をW合格
このような方にオススメの記事です
・民間企業から公務員への転職を考えているけど、自分に向いているかな?
転職は人生の中でも重要な決断のひとつです。
出来るだけ先ゆく人から情報収集して、判断材料を増やしていきたいですよね。
この記事は、公務員に興味を持ちつつ民間企業で働く方、特に40代女性の方にオススメする記事です。
この記事を読むと分かること
・民間企業から公務員になって成功する人、後悔する人の特徴が分かる
公務員に転職して成功する人とは





安定を求めて公務員を志望する人も多いのでは?
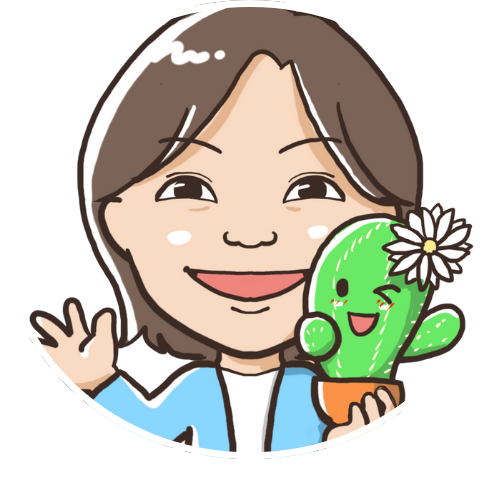
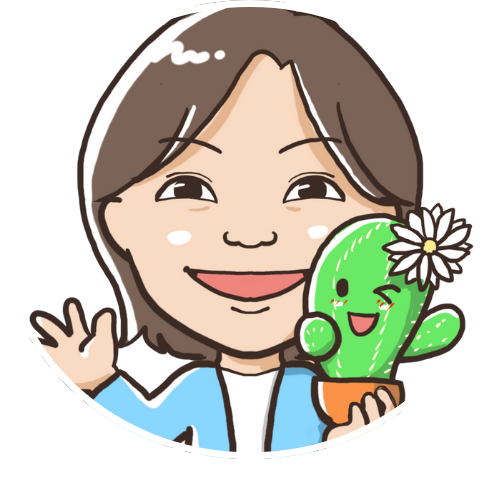
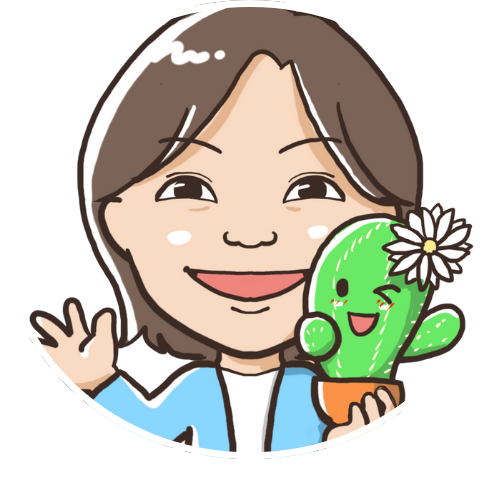
確かに民間企業と違って解雇される心配はないね。
でもだから安泰とも限らないのではないかな。
地方自治体といっても、民間企業と同じで、勤務先として「合う」「合わない」があります。
筆者の同僚で、長く働き続けられている人の特徴は以下です。
1.専門的な職業が活かせる人
地方公務員といっても様々な職種があります。
警察官や公立学校教諭はもちろんですが、都道府県や市区町村の職員においても、行政職以外に、研究職や、医療福祉職など多岐にわたります。
採用試験の際に専門職の区分で応募して採用された場合は、専門職の道を極めることができます。
この場合は、自分の民間企業時代の経験が公務員の職務としても活かすことができます。
自分が発揮できる能力と周囲が求めている能力がマッチするため、転職してもやりがいを持って働ける可能性が高いでしょう。
2.集団の中で切磋琢磨するのが好きな人
あなたは、学生時代はクラスの中でどのようなポジションでしたか?
- 生徒会長や部活動の主将を任されるリーダータイプ
- クラス内のどのグループの子とも仲良くできる八方美人タイプ
- 文化祭や修学旅行、交流試合などのイベントが好きなお祭り人間タイプ
公務員は大きな組織の中のコマとして忠実に上層部の意向に沿うことが求められる仕事です。
「納得はいかないけど、我慢しよう」という意識でも、ある程度は働き続けることはできますが、無理は少しづつ蓄積し、いつか心身の不調という形で表れてきます。
このため、学生時代から、所属する組織において自分の役割を主体的に見つけて、やりがいを持って何かを達成した成功体験のある人は、公務員としても無理せず楽しんで活躍できると考えます。
3.自己開示力が高く、組織の中でも常に自分中心でいられる人
公務員は毎年、人事異動があります。
自分には異動の内示が出ず「残留組」になっても、周囲の人は変わりますし、担当する業務が変わる場合があります。
このため、年度が変わって急に、職場環境や人間関係の変化でストレスを感じるようになることもあります。
前年度に一応、イベントとして異動希望のヒアリングはありますが、希望が通る保証は全くありません。
一方、苦手な業務を任されるとすぐに医師の診断書を上司やに突きつけ、担当業務を見直してもらったり、周囲の人に任せることができる同僚がいました。
「自分は、民間企業ではやっていけないから、公務員としてとにかくしがみつくんだ」
これが彼のポリシーでした。
そのように、自分のネガティブな要素でもユーモア交えて明るく自己表現できる人は、生き残れるでしょう。
公務員に転職して後悔する人とは
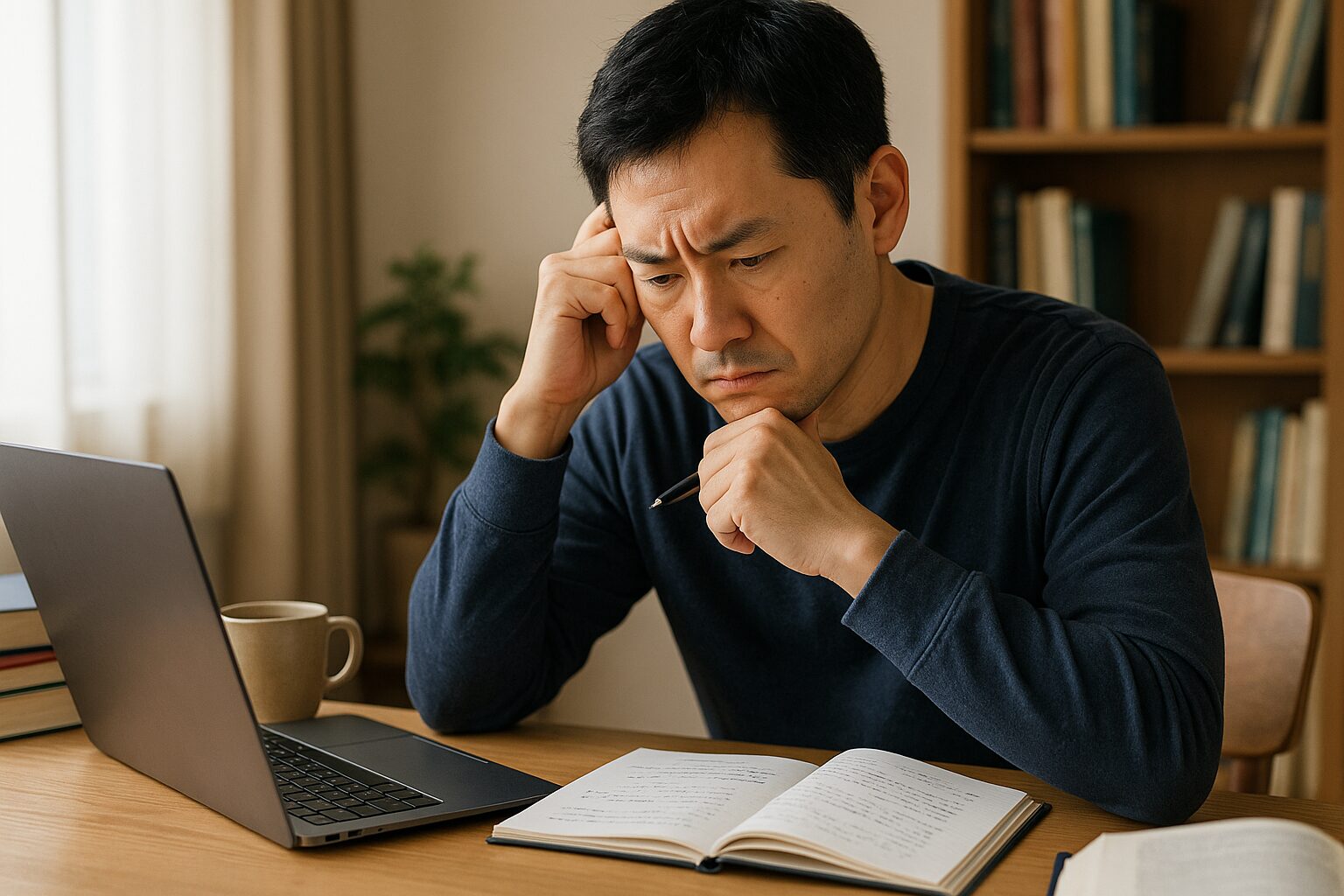
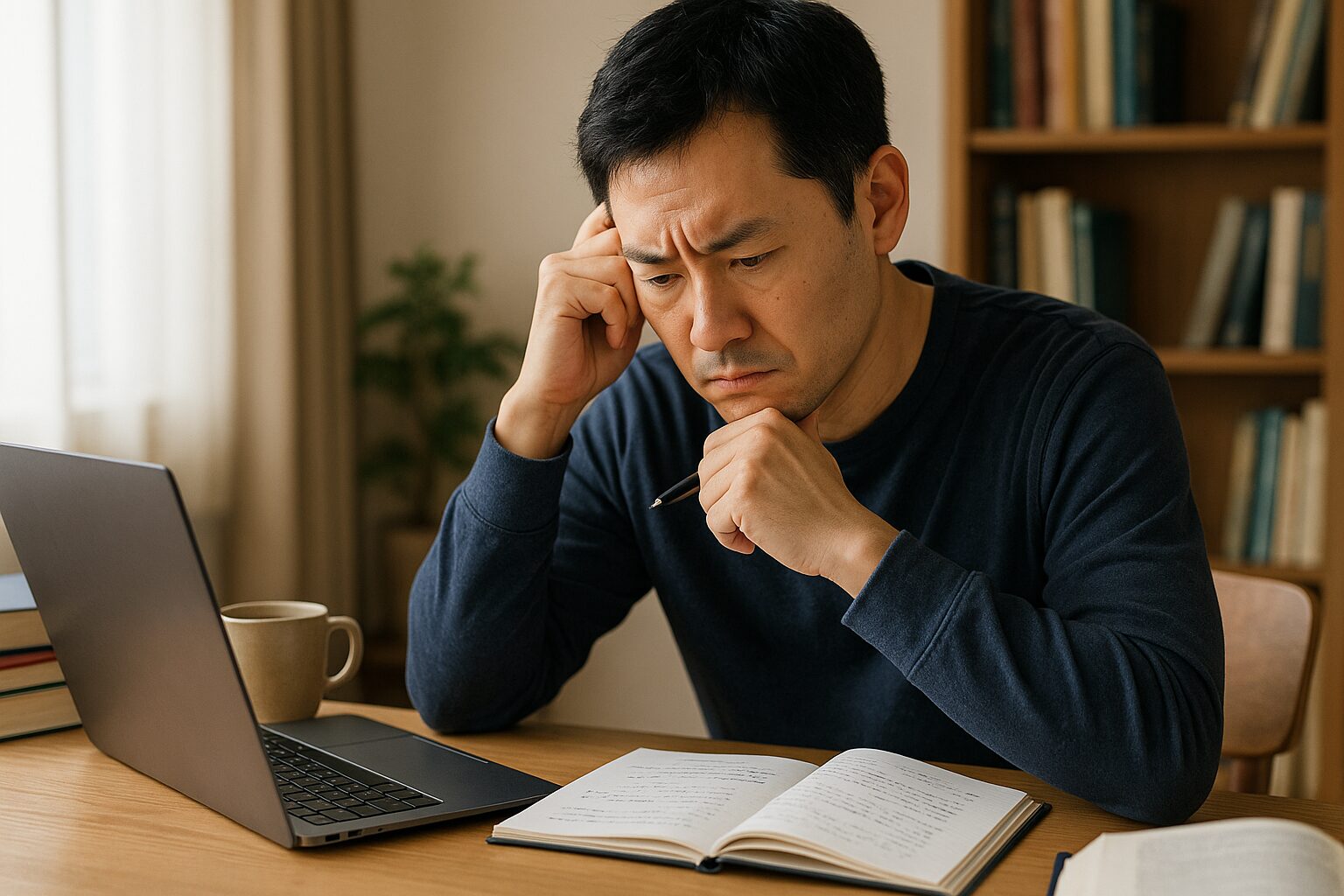
次に、公務員に向いていない人はどのようなタイプでしょうか。
1.環境の変化が苦手な人
地方自治体の庁舎は、東京都庁のように立派な建物もあれば、築40年超のボロ建築の場合もあります。
特に、昔からの建物は国の指定文化財に指定されているという理由で増改築がされずに、観光名所としては素敵だが、毎日働くには不向きな場合もあるのです。
また、改築の予算がつないため、昭和レトロな風合いを残している建物もあります。
職場環境、温度変化、周囲の騒音などに敏感な方は、事前に受験対象の自治体の庁舎を下見しましょう。
その庁舎で自分が働いているイメージを持つことができるかを考えることをお勧めします。
2.仕事にこだわりを持つ人
一般行政職の公務員は、通常は数年ごとに異動があります。
人事異動は毎年行われるので、自分は現組織に残留の場合でも周囲の人が変わるため、実質毎年新しいグループで仕事をするような環境も珍しくありません。
上司が変わる、部下が変わる、自分自身が全く未知の部門に異動する、毎年常に、そのような変化がつきまとうのです。
後輩から業務を教わったり、上司の指示が去年と変わることもよくあることです。
このため、自分の仕事のやり方に固執していたり、変化に対して保守的に身構えてしまうタイプの方は適応が難しい場合があります。
現在の仕事を鑑みて、毎年流動的に組織が変化する体制に慣れることが出来るかどうか考えてみましょう。
3.プライド高く、自分成果主義の人
公務員の業務は「文書主義」「決裁主義」が基本です。
昨今は、民間のDX推進の風潮を受けて、ペーパレス促進の流れが進んでいますが、それでもWord文書を印刷して関係者の承認印をもらう「決裁」は無くなりません。
理由は、公務員は個人の力ではなく、組織としての仕事になるからです。
例えば、あなたが県民相談課の窓口担当だとしましょう。
そして、県民から県行政に対する改善要望書を受け付けたとします。
県民が求めているのは、職員の個人的な見解ではなく「県庁という組織としての回答」ですよね。
このためまずあなたは、多くの関係部局に回答作成を依頼します。
次に、それを取りまとめて回答案を作成し、関係部局の担当者に内容の確認及び承認を依頼します。
各部局の担当者の確認結果を自分の回答案に反映した後、決裁のルールに従い、関係者に決裁依頼を回すのです。
そして、最終的には事務決裁規定に基づく決裁権者の承認を得ることになるのです。
この過程で、あなたの作成した回答文が大幅に修正指示されることもあるでしょう。
民間企業出身の場合は、行政文書の独特のルールに慣れていません。
「君は基本的な作法も知らないのか」と叱責されても、素直に謝り修正する姿勢が必要です。
事実、筆者も「て、に、を、は」や句読点の打ち方、漢字か平仮名か、というレベルの修正も数多く頂いて修正してきました。修正してもさらに上の立場の人の指摘で、全く逆の指示を受けて、いちから作成し直しになることさえあります。
自分のプライドに固執して指摘を素直に聞き入れられない人や、「こんなくだらない修正は時間の無駄だ」と考える成果主義の人は、公務員文化に適応が難しい可能性があります。
結局は「郷に入りては郷に従え」が重要


もちろん自分の仕事にプライドと熱意を持って一生懸命取り組む姿勢は、社会人の基本として必要です。
このため、ただ相手の言うことに迎合し、盲目的に従うのではいけないでしょう。
相手の指摘に対し反論する必要がある場合は、適切な形で議論し、お互いより良い形で仕事を進めていくよう努力する必要があります。
結局は、自分が所属している組織に愛着を持ち、周囲の人に興味と関心を持ってコミュニケーションをとりながら仕事に取り組む姿勢が成功の秘訣でしょう。
よくある質問
まとめ


民間企業からの転職組でも、生き生きとやりがいを持って働いている公務員も大勢おります。
また、公務員は、安定、給与、福利厚生というメリットも多いことも事実です。
もし、あなたが、我こそは!という熱意をお持ちでしたら、ぜひ、公務員にチャレンジすることをおすすめします。